「三輪山本」という超高級そうめんブランドがあります。その「三輪山本」について考察し、PRします。
さて、「三輪山本」を語る前に、今回は「三輪」と「そうめん」について、そのルーツから、できるだけ簡単に解説したいと思います。
三輪
「三輪」とは奈良県桜井市にある三輪地方のことで、現在の「奈良県桜井市三輪」という土地区画よりは広く、三輪山の西側の山麓に広がる1辺が2kmほどの三角形のエリアを指します。

この三輪という土地は、実は、由緒の正しさで言えば日本屈指の豊かな来歴を蓄えた地域です。田畑を耕せば縄文や弥生の土器が欠片が見つかるような土地です。それは、前回の#1で名前を挙げました纏向遺跡とか箸墓古墳などの卑弥呼の時代の遺構がそこにあることでも明らかなのですが、ヤマト政権がその最初期に都を構えた場所がここでして、言うならば日本のルーツのような場所なんです。現在ではわずかに三輪山が「日本の神棚」としてその面影を残しているのみですが、三輪は日本にとって大きな意味を持つ地名です。

で、「三輪そうめん」は、その三輪という、かなり大仰な名前を冠している訳です。三輪は、当然ながら、粉食や麺類などを含めた日本のほとんどの食文化の発祥の地でもありますから、お尻にそうめんが付いたって別に構いやしないんですが、前部分と後部分のスケールの差がちょっと大きすぎて、アンバランスな感じがしないでもありません。
神酒
三輪の名前は当然ながら万葉集の中にも出てきます。
味酒呼三輪之祝我忌杉手触之罪歟君二遇難寸(うまさけを三輪の祝が斎ふ杉手触れし罪か君に逢ひがたき)
という相聞歌(恋愛の歌)が有名です。この歌を誤訳覚悟で現代の言葉にしますと「大神神社の神官らが祀るご神木の杉のような高貴なあなたと関係を持てたのに、身分差がありすぎてバチが当たったのか、もう逢うことができない。」みたいな歌詞で、周囲と恋愛マウントを取り合うような女子女子した内容なんですが、ここで出てくる味酒(うまさけ)は三輪の枕詞です。

三輪の大神神社の御神体である三輪山は「酒の神様」として有名です。大神神社では毎年11月14日に全国から蔵元や杜氏が集まる「醸造祈願祭」が行われています。また醸造祈願祭の後に全国の酒蔵へ杉玉が配られるそうで、造り酒屋さんの店先などの軒先に吊られて新酒を知らせる杉玉も元々三輪から始まった文化だそうです。
神々への奉納や祭りの際に用いられるお酒を指して、「神酒」と書いて「ミキ」と読みますが、「ミワ」とも読みます。つまり、「神に捧げるお酒=ミワ(三輪)」でして、三輪山が酒造りの神聖な場所として長い間尊ばれてきたことは確かです。三輪山は古代から信仰の対象で、様々な呼び名が付けられたのですが、その一つが三諸山で、「うま酒みむろの山」と称されます。「みむろ」は「実醪」すなわち「もろみ(醪)」のことで、酒母・麹・蒸米・仕込み水をいれた発酵中の液体、つまり「酒のもと」の意味です。個人的な妄想ですが、三輪あたりが大和の中心であった時代に、多分王宮お抱えの渡来系の醸造技術者が麹カビを使った酒造りを日本の風土にあった方法に改良して、現在につながる醸造技術がはじまったのではないかとも思えます。

何にせよ、三輪山に対する信仰の古さは、あの伊勢神宮が新設の神社に思えるほどに深い歴史があり、境内には徳川四代将軍家綱が寛文四年(1664年)に建立した豪壮な拝殿があるのですが、自然の機微に畏怖を感じる古代信仰の聖地にあって、その築350年以上の威容は何だか無駄にゴテゴテしていて、場にそぐわないように感じてしまいます。
そうめん
で、次は「そうめん」について、駆け足で解説します。
有職料理
「そうめん」は、遣隋使のような使節団が持ち帰った索餅(さくへい)をルーツにもつ、日本最古の麺食品と言われています。しかし索餅との関係は、その呼び名以外はちょっと希薄で、共通しているのは、両方とも小麦粉を使った外国由来のレシピで、公家料理だという点くらいです。しかし、何と言うか、公家というのは日本の貴族のことですから、索餅にせよそうめんにせよ、わたし達のような庶民には馴染みのない料理でした。知名度というか、一般人の生活に根付いていたのはうどんで、今だにわたし達がうどんのほうをより身近に感じる原因は、此処にもあるのかも知れません。が、意外なことに歴史の深さではうどんより圧倒的にそうめんです。何にせよ、そうめんという食べ物は専ら公家が食べる程度で、公家以外では寺方くらいしか口にしませんでした。

そうめん作りには時間がかかります。コスパとタイパを考えると、そうめんは最悪の麺です。寺方、つまりお坊さんたちの食事といえば、今でも精進料理のイメージがありますが、彼らは「食も修行の一つ」と捉えて凝ったことをしますから、公家が食べるようなレシピでも作ってました。乾麺に加工する技術が伝わってからは備蓄の意味合いも生まれたかもしれません。それでも彼らの食事は修行の一環ですから、基本的には生産から消費まで寺院内で完結してしまいます。そう云う「閉じられたレシピ」ですから、仮に俗人に振る舞われることがあったとしても賓客くらいにしか振る舞われることがなかったでしょう。庶民には広まりませんでした。まあ、仮に庶民がそのレシピを知ったところで、だいたい彼らは日々の生活に追われてますから、食事に無駄なコストを掛けるような余裕はなかったでしょう。
調
しかし、寺方はさて置き、お公家様方は自分でそうめんは作りませんから、三輪では日本の最初期あたりの昔から、庶民がそうめんの生産に携わっていました。日本では古くから麦と言えば大麦。小麦は粟や稷に比べても圧倒的に人気のない雑穀でしたが、三輪では盛んに作られていたようで、ここからは想像ですが、はじめは小麦をそのまま王宮に納税していたのかもしれません。それが都が引っ越しをした際に、回転式の石臼(挽き臼)が残されて、今度は小麦を挽いて粉にしてから納品するように課税内容が変更されたのかもしれません。さらに乾麺の技術が伝わってくると、製麺して完成品にしてから上納するスタイルにさらに変化したのかも知れません。租庸調の納税慣習では納税者側が都まで納税品を運びましたから、納める側としてもできるだけ完成品に近づけて無駄なく運びたかったでしょう。いずれにせよ、江戸の初期には、三輪の人々は農閑期にそうめんを作ってはそれを都に運ぶことが習慣になっていました。無論、自分達では食べていませんでした。
年貢
わたし達のような庶民の口にそうめんが届くようになるのは江戸時代になってからの話で、まずは#1でも簡単に触れましたが、八代将軍徳川吉宗による幕府の財政基盤の強化策と享保の改革で、三輪にそうめんの大規模な生産が求められるようになりました。それまでそうめんを作るための場所やら道具を管理して公家に納めていた地元の庄屋は、量産体制を構築する元締めを命じられ、そうめんメーカーの責任者のようなものになり、毎年変動しながら求められる課税量を幕府に納入する義務を負いました。このトップバッターとして任命された庄屋が三輪山本の山本家です。幕府は大和や近畿の農民に小麦の二毛作を奨励し、各地で収穫し製粉された小麦粉を材料として仕入れ、三輪で精製し、そうめんに加工する家内制手工業のような生産システムが出来上がりました。

蛇足ですが、江戸幕府は便槽の普及も推進していました。汲み取り式のボットン便所で効率よく屎尿を貯めて、それを肥だめで熟成してから散布する技術は二毛作には必須条件でした。「下肥買い」や「灰買い」といった屎尿をや炊事で出る灰を商売にする人などが江戸時代には活躍していて、資源を循環させ、公衆衛生と農業生産を支える需要な役回りを果たしていました。
名物
さて、三輪に無事そうめん業者が産まれたわけですが、上納する量が命令を下回れば彼らは役人から大目玉を食らいますから、庄屋は常にそうめんのストックを抱えることになりました。無論、その前からある程度の余剰在庫はあったでしょうが、規模の桁が違います。で、これが新しいムーブメントを生み出しました。

ちょうどこの頃には、太平の世にすっかり慣れた庶民の間で、新しい娯楽として国内観光ツアーが流行していまして、その大人気スポットの一つが伊勢神宮でした。有名な「お伊勢参り」です。このお伊勢様に西廻りで参拝するツアーのルートがちょうど三輪を通っていまして、三輪にも大神神社や長谷寺という人気の参拝スポットがありましたから、三輪はその頃には宿場町に準ずるような発展を見せていました。この観光客を相手にそうめんを食べさせ始めたのです。庶民にとってそうめんは超高級食品なんですが、一生に一度かも知れない旅先での食事ですし、名高い三輪の名物ということで、ツアー客たちはこれを喜んで求めました。で、美化するような心理的なバイアスも働いたのでしょう、土産話として西の庶民に「お公家様の食べる冷や麦はそうめん言うて、そりゃぁお上品でド偉い美味いらしいで!」と認知されはじめました。実際にお土産で持ち帰るツアー客もいたでしょう。コアなファンも出来まして、小豆島も播州も、現在有名な多くの素麺産地の製造ノウハウは、素麺に惚れ込んだお伊勢参りの観光客が、帰路の途中でそのまま三輪に居座り数年間修行して、「暖簾分け」のようにその技術を持ち帰って作り始めたものです。

「お伊勢参り」というツアーの人気たるや、ちょっと想像を絶する程度でして、江戸時代の国学者本居宣長の『玉勝間』には、1625年の50日間に合計362万人がお伊勢参りしたと記録されています。特に60年に一度の周期で3回起こった「おかげ参り」では、数百万人の人々が集団参詣したそうです。当時の日本は人口が3000万人程度の国ですから、その異常な人気ぶりが伺えます。

普及
ここから先は想像でしかないんですが、この三輪そうめんを庶民に普及させる際の販促活動として、かつて索餅からそうめんに変化しながら魔除けとして宮中で続けられてきた七夕の神事を喧伝して「七夕にそうめんをお供えすると魔除けになるし、針仕事なんかも上達する。」などと吹聴したのではないかと思います。また、七夕とお盆をセットにして「七夕のついでにお盆にもご先祖様をお迎えするために仏壇にそうめんをお供えすると縁起が良い。」などといったキャンペーンを三輪のそうめん茶屋なんかが銘打ったんじゃないかと思います。縁起物も季節イベントも庶民の大好物きですから、このキャンペーンはツアー客に乗って日本各地に文化的な行事として広まり、日常食としては成立しないはずの高価なそうめんの需要が庶民に広まったのでしょう。

そして暖簾分けされた地方のそうめんも、贈答品や供物としてのそうめんの需要の高まりと共に生産規模を拡大していきました。狭い三輪での生産拡大はすぐに頭打ちになったはずで、この辺りからそうめんの中で三輪がブランド化していったと思われます。また、淡路島や小豆島に暖簾分けされた技術がさらに徳島や島原に渡るという「二暖簾分け」ような現象まで起きました。
ただし、様々に暖簾分けされた各地のそうめんですが、その地位を確かなものに出来たのは明治に入ってからだと思われます。
ジョニ黒
例えを挙げると、太平洋戦争の敗戦後から海外旅行が自由化されるまで、海外土産の定番が「ジョニ黒」だったことがあります。星の数ほどあるウィスキーの銘柄の中で、ジョニーウォーカーだけが持て囃され喜ばれたという今から見ると不思議な現象なんですが、中でもその黒ラベル(通称「ジョニ黒」)は庶民の憧れでした。
この現象は、大日本帝國の時から政府が国民の購買意欲を削ぐために贅沢品に対して高い税金を掛け続けていたこと、その傾向が輸入ウィスキーに特に顕著だったためで、庶民は国産のウィスキーしか知りませんでした。この国産「ウィスキー」というものは、醸造アルコールにウィスキーを少量足して色素と香味料を加えたもので、含まれるウィスキーは高価なもので30%(特級)ほど。庶民が飲める値段のウィスキーとなると、限りなくウィスキーの成分が0%に近い、もしくは0%のものが「ウィスキー(二級)」でした。

そんな中、客寄せの看板的に店舗に並べられる定番の輸入ウィスキーがありました。進駐軍や米軍基地で米兵によく飲まれていたことで馴染みのあったジョニーウォーカーです。当時の大卒初任給二ヶ月分に相当する価格だったので、日本人が買える酒ではなかったのですが、露出の多さから庶民の知識の中で「洋酒代表=ジョニーウォーカー」という図式が出来上がり、ウィスキー好きは国産の混ぜものウィスキーを呷りながら「俺もいつかはアイツを!」と憧れを抱いていました。

ところが旅行や出張で海外に渡航する人たちは、空港などで免税品が買えます。ここでダントツに人気だったのが日本国内で抜群に知名度を誇る洋酒代表のジョニーウォーカーで、さらに課税後なら絶対に買えない高級レーベルである「黒」が人気でした。帰国した友人や上司から「ジョニ黒」の土産を受け取った人は狂喜乱舞したものです。

その後、ジョニ黒信仰が終焉したのは1971年のウイスキー輸入自由化からで、ジョニーウォーカーの他にも「オールドパー」、「バランタイン」、「ホワイトホース」、「シーバスリーガル」なども台頭して、1980年代には舶来ウイスキーブームが起こりました。そしてブームが去った後の1989年には酒税法が改正され、ウィスキーの特殊な税制も廃止されました。今や国産の粗悪ウィスキーは絶滅し、ウィスキーの棚には国内外の個性あふれる様々なボトルが並びます。ジョニ黒は現在も多くのファンを持つ銘柄で、数あるウィスキーのワンオブゼムとして洋酒の店に並んで販売されています。ちなみにわたしはウィスキーなら「メーカーズマーク」というバーボンが良いです。
独歩
さて、話をそうめんに戻しますと、これとほぼ同じ図式が三輪そうめんにも当てはまると思います。江戸時代の中期頃から観光ツーリズムが流行ったと言っても、それは宗教的な参拝などに目的を限った話で、藩を跨いでの人々の移動は本来には厳しく制限されていました。そのような環境下で、西廻りのお伊勢参りツアーの土産として三輪そうめんが大変に重宝され、また大いに喜ばれたということです。そして、廃藩置県後に県を跨いだ人の移動が自由になると、そうめんは三輪以外でも産地がありますから、三輪の一極集中は徐々に収束し、その冷める熱と反比例するようにそうめんの本格的な普及が始まったと思われます。贈答品にまだバラエティが少なかった明治から昭和の高度成長期までの長い期間をかけて、紆余曲折を経ながら、お中元のド定番として確固たる地位を確立しました。

ただ、その中で「三輪」の地位がイチ生産地として他の地域のそうめんと横並びになったかと言うと、そうはなりませんでした。そうめん産地の広がりを円で例えると、その中心の三輪だけがまるで画鋲の針のように長いルーツをもっていましたから、逆に良くも悪くも別格として残りました。具体的には、各地方のそうめん産地が「揖保乃糸」に代表されるように地域で生産ブロック化していったのに対して、三輪ではそうめん業者でまとまろう!という気運が他の地域に比べてかなり低く、個々のメーカーが独立独歩で競合関係にありました。「山本(三輪山本)」などは既に全国規模の知名度だったはずですから、江戸時代に茶屋で観光客にそうめんを食べさせていた頃より、三輪の製麺業者はお互いをライバルとして視ながら成長していったのでしょう。
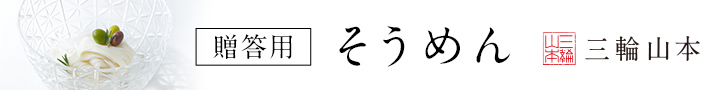
#3に続きます。
参考文献
石毛 直道 「麺の文化史」
奥村 彪生 「増補版 日本めん食文化の一三〇〇年」
松本 忠久 「めんと和菓子の夜明け: 索餅の謎を解く」
木村 茂光 「雑穀: 畑作農耕論の地平 (ものから見る日本史)」
参考サイト
Wikipedia、国立公文書館、国立国会図書館、国土地理院、三輪山本、ジャパニーズウイスキーデータベースwiki、日本建築学会計画系論文集 第79巻 第700号,1433-1439,2014年 6月J. Archit. Plann., AIJ, Vol. 79 No.700, 1433-1439, Jun., 2014,是澤紀子,近世初期三輪山における禁足の制定とその景観 神社の禁足地とその景観に関する研究、国税庁/酒税が国を支えた時代、瀬戸の島から 金毘羅大権現形成史1-2 金毘羅さんは、天狗信仰=修験の山だった。、今西酒造株式会社 酒と三輪の歴史、奈良県立万葉文化館 万葉百科 歌詳細、國學院大學デジタルミュージアム 所蔵古文書データベース 万葉集神事語辞典、宝酒造 酒噺 ~もっとお酒が楽しくなる情報サイト~ 知っているようで知らない“杉玉”の噺、奈良県 みわ-三輪の由来、など。
画像、動画元サイト

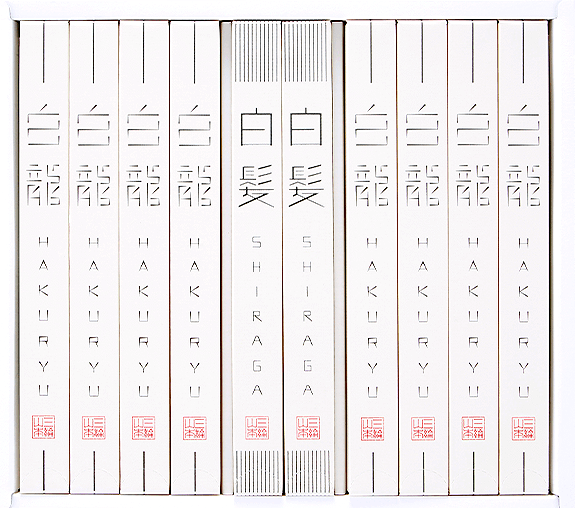






コメント